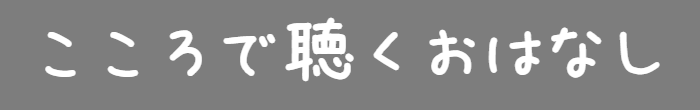●信者さんのおはなし
「悲しいけれどそれは母の最後の親孝行でした」

東京都
金光教東京教会
関口昭子 さん
「もし、地震や火事になったら、私に構わず、あんた一人で逃げなさい」。
20年前手足の関節をリウマチに冒され、一人では身動きできなくなった叔母の、何気ない言葉でした。
その時私は、何を唐突に叔母が言い出したかと、深く考えもせずに受け答えしていました。それから間もなく叔母は、後に残る私に切ない思いをさせないように、全てに気配りをして他界しました。私にとっては母親代わりの叔母でした。
私の母は太平洋戦争の始まる昭和16年、それまでの心労が重なったためか体調を崩していました。何か胸にしこりがあるのを気にして、人の勧めもあり、検査を受けました。即、乳がんを宣告され、直ちに手術。しかし、かなり進行していたがんは時を待たず、リンパ節を伝わり転移。もちろん当時のことで抗がん剤はありません。本人も家族も「がん」の宣告は「死」と受け止めたことでしょう。
しかし、当時10歳の私には母親が死の病と闘っているなど見当もつきませんでした。
そんな時、日本はアメリカやイギリスと戦争を始めました。帝国日本は負けないと、私たち小学生も、お国のために役に立とうと励みました。
そして、昭和17年4月18日。東京の上空にアメリカの爆撃機が襲来し、爆弾を投下していきました。これが、東京空襲の第一歩でした。
当時食糧は既に配給制度となっていました。その日私は配給の卵をザルに入れて家に帰る途中、空襲のサイレンを聞きます。思わず見上げた空に1機の飛行機が見えましたが、それがこの爆撃機かどうかは分かりません。ただ、ボーッと空を見上げていたように思います。
そして、その時を境に私たちの生活は一挙に様変わりしてゆきます。
町内近隣同士の結束。隣組という組織の下に空襲に備えての訓練。バケツリレーの水で火を消す。果ては竹槍で人を刺す練習が毎日のように行われました。
一方、我が家では手術後の母を、祖母、曾祖母、そして叔母の3人が交替で看病しました。その間を縫うように隣組の責任者となった祖母は、出征兵士を送る指揮を執ったり、だんだん少なくなる男たちに代わって隣組の仕事も増え忙しくなりました。「病人がいるから」など口実にもなりません。そういう中で、母は昭和17年8月、37歳の若さで亡くなります。その時、76歳の曾祖母は「私が代わってやりたかった」と泣きました。
その曾祖母も翌年9月、3日間床に着いたきりで、この世を去りました。
「親より先に死ぬ親不孝」と言われる程、祖母にとって、37歳の母の死は、辛く悲しい野辺送りだったと思います。しかし、11歳の私にはそんな祖母の胸のうちを計ることさえできず、ただ悲しみに打ちひしがれていました。そんな私に、一緒に泣きたかったはずの祖母は「泣いたってお母さんは帰っては来ない!」と私をしかりました。
いつ襲ってくるやも知れない空襲に備えて、東京の空の下で私たちはおびえながら暮らす毎日でした。そんな中でも、悲しいけれど2人の葬儀は無事に、しめやかにそれぞれさせていただくことができました。
やがて、人が亡くなっても葬儀をすることなどできなくなる時が、すぐ目の前まで来ていたのです。
昭和19年後半から20年になると、連日連夜といえる程の空襲に見舞われ、特に昭和20年3月10日の東京下町の大空襲は、この戦争にとどめを刺すほどの大規模なものでした。それでも戦争は続けられました。
遠く沖縄ではもっともっと悲惨な事態が繰り広げられていました。そしてついに世界で初めて原子爆弾が広島、長崎に投下され、ようやく戦争が終わりました。
もうそのころは死者を丁重に弔うなど考えもつかない日々でした。つい今まで一緒に居た家族が、その生死すら確かめられず、黒こげの遺体を見てもどこの誰かも分からず…。そんな悲劇がたくさんこの戦争によってもたらされたのです。
父親を病で亡くした友人は「遺体を納めるお棺が無くて、やむを得ず天井板をはずしてお棺にした」と、うつろな目で語りました。
もし母が、あの空襲激しい中、病の身で横たわっていたなら、きっと、叔母が私に言ったように「私を置いて逃げて」と叫んだでしょう。
あの時母は、親よりも先に死ぬことは親不孝だと世間の人たちから言われたかも知れないけれど、母にとっては〝悲しい最後の親孝行だったのではないか〟と私は思うのです。
病んでいる娘に「私を置いて逃げて」と言われ、そして我が子の葬儀すらできずにいたなら、祖母は親としてどんなにか嘆き、悲しんだことでしょう。
このような体験をした人はきっとたくさんいたに違いありません。誰もがそんな体験はしたくはないし、この地上に住むすべての人々にさせたくありません。
だから私は、いえ私たちは「戦争の被害者にも、加害者にもなりたくはありません。絶対に!」と、亡くなられた人たちとともに叫びます。
金光教には「人が人を助けるのが人間である」という教えがありますが、人間だからこそ人を助けることができるのです。その本来あるべき人間の姿を取り戻すことが何よりも大切だと思うのです。